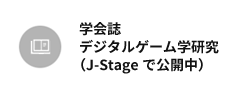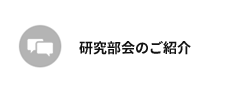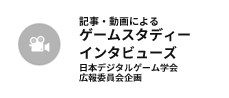投稿日:2023年2月4日
2月24日(金)、25日(土)に 日本大学理工学部駿河台キャンパス(東京都千代田区)にて開催される、日本デジタルゲーム学会 第13回年次大会の参加申込を開始しました。

本大会のテーマは「デジタルゲーム学研究 × 新たな挑戦」 です。
宮田章裕氏(日本大学) による基調講演「弱さと向き合うコンピューティング」(2/24 13:45〜) の情報 や当日の大会プログラムも含め、下記URLの大会Webサイトにてご確認ください。
https://digrajapan.org/conf13th/index.html
なお、事前参加申込は2月23日まで(銀行振込の場合は2月22日まで)になっております。当日会場での参加申込も可能ですが、参加費が10,000円となりますので、事前のお申し込みをお願いいたします。
みなさまのご参加をお待ちしております!
投稿日:2022年11月17日
2023年2月24日(金)・25日(土)に 日本大学理工学部 駿河台キャンパスにて開催される日本デジタルゲーム学会 第13回年次大会の演題申込の受付を開始しました。
詳細はこちらのCPFページをご確認ください。
https://easychair.org/cfp/DIGRAJAPAN-13TH
申込締切は、「特選セッション(査読付き)」と企画セッションは2022/12/20(火)、それ以外の発表は2023/1/16(月)です。
皆様の研究成果の発表をお待ちしております。
投稿日:2022年11月7日
日本デジタルゲーム学会は、2023年2月24日(金)・25日(土)に 日本大学理工学部 駿河台キャンパス にて、第13回年次大会を開催いたします。
【大会概要】
日時:2023年2月24日(金)・25日(土)
場所:日本大学理工学部 駿河台キャンパス
https://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/surugadai/
〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台1-8-14
JR中央・総武線「御茶ノ水」駅 下車徒歩3分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 下車徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 下車徒歩5分
内容:・全体会企画・特選セッション(査読付きセッション)発表・一般セッション発表(口頭発表セッション、インタラクティブセッション、ライトニングトークセッション、企画セッション)
また、本日CFPを公開いたしました。詳細は下記ページをご確認ください。(11/17 発表申込ページを公開いたしました)
https://easychair.org/cfp/DIGRAJAPAN-13TH
現時点(11/7)では、上記の通り、日本大学理工学部 駿河台キャンパスでの開催を予定しております。
皆様の研究成果の発表をお待ちしております。
投稿日:2022年9月8日
9月4日に開催された2022年夏季研究発表大会ですが、無事終了することができました。
「デジタルゲーム研究の次の一歩へ」 をテーマにした本大会ですが、これまでの研究テーマをさらに発展させてた方から、今回初めてDiGRA JAPANで発表された方まで、様々な方に発表いただきました。
基調講演「デジタルゲーム研究による博士号取得のすゝめ」や、研究の卵を温めるリサーチエスカレーターセッションなど、テーマに合わせた企画も開催させていただきました。
今回も多くの皆様にご参加いただき、ありがとうございました。
○「ゲームと四人」(リサーチエスカレーターセッション 渋谷和也氏発表)
※ご意見が欲しいとのことでしたので、発表に興味を持たれた方はコンタクトをしてみてください。
○日本デジタルゲーム学会 2022年夏季研究発表大会ページ
https://digrajapan.org/?page_id=9334
○ 日本デジタルゲーム学会 2022年夏季研究発表大会 CFP(削除される可能性があります)
https://easychair.org/cfp/DIGRAJAPAN2022-SUMMER
○大会プログラム
ダウンロード
投稿日:2022年7月26日
日本デジタルゲーム学会 2022年夏季研究発表大会(9/4 日曜、オンライン開催)の 参加申込受付を開始いたしました。
詳細な情報は、大会ページ をご覧ください。
参加ご希望の方は、下記URLの参加申込フォームよりお申込みください。
みなさまのご参加をお待ちしております。
参加申込フォーム :
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/apply/DiGRA
参加費:
会 員:一般・発表者※ 3000円、一般・参加のみ 2000円、学生1000円
非会員:一般・発表者※ 4000円、一般・参加のみ 3000円、学生1000円
※ 発表者も別途参加申込を行う必要があります。
※ 「発表者」料金は第一発表者にのみ適用になります。学生は第一発表者も学生料金を適用します。
※ 参加費を口座振込で払う場合は2022年9月1日まで申込、9月2日にお振込みください。
投稿日:2022年7月12日
2022年9月4日(日)にオンラインにて開催される2022年夏季研究発表大会は、 当学会が一般社団法人になってから初めての研究大会ということで、大会テーマを「デジタルゲーム研究の次の一歩へ」 といたします。
そこで、 テーマに沿った形で 基調講演と実行委員会セッション「リサーチエスカレーターセッション」を企画いたしました。
※大会の詳細情報は大会ページをご覧ください。
基調講演
「デジタルゲーム研究による博士号取得のすゝめ」
かつてポケモンマスターをめざしたゲーム研究者が次にめざす目標は、ゲーム研究で博士号を獲得することかもしれません。ゲーム博士は、かつては夢のまた夢のような話だったかもしれませんが、今では日本デジタルゲーム学会内だけでも珍しくなくなっています。一般社団法人になり、新しく覚醒した日本デジタルゲーム学会では、若手のゲーム研究者・開発者、またゲーム研究者や開発者の卵にあたる皆さんを、全力で応援していきたいと考えています。
その応援の第1弾として、最近ゲーム研究で博士号を獲得した「ゲーム博士」の2名に基調講演をお願いします。博士論文の内容の一部をわかりやすく語ってもらうだけでなく、苦労した点、工夫した点など、若い皆さんへの熱いメッセージをお届けできればと思います。
講演者
粟飯原 萌 氏(日本大学)
シン・ジュヒョン 氏 (立命館大学)
リサーチエスカレーターセッション
3分程度、研究のアイデアの提案、研究に発展しそうな事例報告、研究の経過報告、作品の発表など、初期段階の研究アイディアの発表を行うセッションです。一つのセッションの中で複数の発表が行われます(先着10名程度まで)。想定される発表者は大学生、大学院生、ゲーム開発者、社会人などで、気軽な発表の機会としてご活用ください。
発表者が専門領域のゲーム研究者・開発者と議論しネットワークを構築できるような場を提供し、研究の発展を支援する機会を提供できればと考えています。当日はリサーチエスカレーターセッションで発表していただいた後、発表者専用のスペースをネットワーキングセッション(懇親会)にて作成いたしますので、そこで議論を深めてください。
○発表形式
発表3分、コメント3分以内。その後の「ネットワーキングセッション」(懇親会)でのコミュニケーションを推奨。
発表用スライドの形式は自由(発表者に操作していただきます)
○申込方法
こちらの申込受付フォームからお申込みください
受付時に「トークタイトル」「キーワード(5つくらい)」「氏名」「所属」「連絡先メールアドレス」「備考」を入力いただきます。
※ゲーム研究の手がかりについては
ゲーム研究の手引き
ゲーム研究の手引き II
ゲーム研究関連リスト – Nobushige Kobayashi’s Website (wordpress.com)
https://chimarisan.wordpress.com/lists/
もご覧ください。
投稿日:2022年5月28日
日本デジタルゲーム学会は、2022年夏季研究発表大会を、9月4日(日曜日)にオンライン開催いたします。
当学会が一般社団法人になってから初めての研究大会ということで、大会テーマを「デジタルゲーム研究の次の一歩へ」 となりました。
募集する発表形式は、1)口頭発表、2)インタラクティブセッション、3)企画セッション になります。発表申込締切は7/17です。
詳細は、下記CFPページをご確認ください。
https://easychair.org/cfp/DIGRAJAPAN2022-SUMMER
投稿日:2022年2月10日
2月11日、12日に開催される第12回 日本デジタルゲーム学会 年次大会の基調講演ですが、以下の内容で行われます。
「人生を何度もループしたらパンデミックは抑えられるか?」
講演者:瀬名秀明氏 (作家)
指定討論者:浅田稔氏 (大阪国際工科専門職大学)
講演日:2022年2月12日11:30~13:00
「関西におけるゲームデベロッパーのリレーションに関して」
講演者:松下正和氏 (株式会社ヘキサドライブ)
秦泉寺章夫氏 (株式会社クラウドクリエイティブスタジオ)
講演日:2022年2月11日13:10~14:10
基調講演の様子は当日、Zoomウェビナーにて、大会に参加されていない方もご覧になれます。(講演の様子のアーカイブ公開は行わない予定です)
ZoomウェビナーのURLは
年次大会Webページ
https://digrajapan.org/conf12th/index.html
をご確認ください。
※大会自体の参加申込は締め切っております。
投稿日:2022年1月13日
2月11日(金 ・祝)・12日(土)開催の日本デジタルゲーム学会第12回年次大会は対面型での開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス「オミクロン株」の流行状況の急激な変容に鑑み、完全オンラインでの開催に変更させていただくことになりました。
第12回年次大会では、With コロナ時代の研究活動を模索すべく対面型での開催準備を進めておりましたが、皆さまのご健康を最優先とし、オンライン開催への変更が適切と判断致しました。非常に判断が難しい状況下ではありますが、このような決断に至りましたこと、ご理解を賜れれば幸甚でございます。
今回の開催形式の変更に伴い、発表者、参加者の皆様の報告準備や参加方法にも影響が生じるかと存じます。深くお詫び申し上げます。
参加申込は以下のフォームからお願いしたします。
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/apply/DiGRA
画面上部に「オンライン参加登録システムにログインするためのIDとパスワードをお持ちですか?」という選択肢がございますが
・日本デジタルゲーム学会の会員あるいは、非会員で本システムに登録済の方は「はい」を選択してください。(会員のIDは1月中旬に配信のニューズレターの文末に記載しています)
・非会員で本システムに初めて登録される方は「いいえ」を選択してください。
大会に参加するには、参加費が必要となります。
参加登録フォームにて登録後、指定の方法(クレジットカード/口座振込)でお支払いください。
大会参加申込締め切りは2月7日(月)、支払い締め切りは2月8日(火)です。
締め切り日より翌日以降の申込、お支払いはできませんのでお早めのご登録をお願い致します。
申込後、自動返信メールにて、ZoomのURLや予稿集など大会参加者向け情報を掲載するwebページのURLをお送りいたします。(情報は随時更新していきます)
自動返信メールが届かない場合は、 conf12thあっとdigrajapan.org まで問い合わせをよろしくお願いいたします。(あっとは@に変更して送信下さい)
大会の詳細は、年次大会webページ
https://digrajapan.org/conf12th/
をご確認ください。
基調講演やプログラムなど、随時情報を公開していきます。
みなさまのご参加をお待ちしております。
投稿日:2021年11月3日
日本デジタルゲーム学会は、2022年2月11日(金 ・祝 )・12日(土)に第12回年次大会を大阪国際工科専門職大学で開催することになりました。
本大会は、現地での開催を想定しております。(感染症の状況次第で、完全オンライン形式に変更する可能性があります。2022年1月中旬頃に判断します。)
つきましては、年次大会での発表者を募集したします。
昨年に続きまして本年も「一般トラック」の他に「特選トラック(査読付き)」を募集いたします。
「特選トラック(査読付き)」(査読用原稿締切:12/13(月))
「一般トラック」(企画セッション概要提出締切:12/15(水)、それ以外の発表は12/24(金)/予稿は 1月23日(日) 締切)
※12/13 :企画セッションの締切を12/15に修正しました。
発表申込ページを12/1に公開いたしました。
詳細は下記ページをご確認ください。
みなさまの研究の成果の発表をお待ちしております。